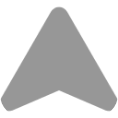般若心経散策(4)

「度一切苦厄」~厄介者の活かし方~第4回
この「般若心経散策」は、『般若心経』の語句を取り上げて、より詳しく見ていくコンテンツです。
「度一切苦厄」の回の締めがこの第4回です。
副題の「厄介者の活かし方」を体現したような逸話を紹介したいと思います。
椋鳩十《むくは とじゅう》(1905年・明治38年~1987年・昭和62年、本名・久保田彦穂、長野県下伊那郡《しもいなぐん》喬木村《たかぎむら》出身)という小説家、動物文学者、児童文学者にこんな話があります。
(講演録『感動は心の扉を開く~しらくも君の運命を変えたものは?』から要約)
椋さんの生まれ育った長野県の下伊那郡は長野県の最南部で、その喬木村というところは下伊那郡のやや中央にあります。赤石山脈の麓でもあり、とにかく山深いところです。
うちの寺のある能登半島も山ですが、海までは比較的近く、5キロほど山を下りると、もう海に出ますので、ちょっと私には想像できない山深さです。
下伊那は、山がちだから平地も少なく、田んぼや畑作できる土地も限られており、椋さんの育った当時は、人々は養蚕をして生計を立てていたということです。養蚕ということは、蚕の幼虫の餌となる桑の葉の栽培をしなければなりません。斜面には桑畑が作られて、その世話のために、人々は何度もきつい斜面を往復します。厳しい労働環境です。そのため、ここの住民は実年齢より老けて見えるそうです。
そんな郷里へ、椋さんは、東京の大学へ進学してから以来約20年ぶりに帰ってきました。初めての小学校の同窓会のためです。見ると先ほどの理由でみんな随分変わっている。だけど、よく見ると小学校時分から変わっていない癖がある。それを目当てに見ていくと、あー、あいつか、と分かってきた。
それで、誰々だったなと、ほとんど分かったけど、一人だけどうしても見当のつかないやつがいた。
背が低くて、色が黒くて、でっぷり太っている。そして立ち居振る舞いといい、椋さんのところへも酒を注ぎに来たけど、何か精神的に押されるような感じがする。こんな特徴のあるやつがいたかなあ、と椋さんは思いました。隣に「あいつは誰だっけ?」と聞いても「あんな有名なやつ、忘れたのか」と言われるだけ。どうしても思い出せません。そしてどこかに特徴が残っていないかと思って顔を見ても、全然思い出せない。
そのうちに、宴席が終わりに近づいて、ぼちぼち帰る者が出始める。そこで隣にもう一ぺん椋さんは聞いてみました、
「あれは誰だっけなかあ?おれは今度戻ったらいつこっちに帰るかわからん。その間、ずっとあれは誰だったかと考えているのは苦しくてたまらんから、教えてくれんか」
と言うと隣の人は、
「何だ、あの有名なやつを知らないのか。ほらほら、あれは“しらくも”だよ」
しらくもと聞いて、椋さんははっと思いだした。そういうあだ名のやつがいたことを。しらくもという頭におできが出来る病気を持っていた同級生。小さい、小指の頭ほどのおできがたくさんできて、白い粉が吹いてくる皮膚病の一つ。それで頭が白く見える、
その病気を小学一年生から六年生までつけっぱなしだった。それでしらくもと呼ばれていたんです。
椋さんの通っていた学校は畑のど真ん中、当時は肥やしに人糞や蚕の糞も使うから、ハエがわんさかいたそうです。いつでも教室の中にはハエが20匹ぐらい飛んでいる。それがしらくもの頭に止まる。ハエは臭うものが好きだから。ずっと止まってればいいけど、ハエだからまたどこかに飛ぶ。しかも、しらくもの白い粉を付けて。給食時間になると、大変です。弁当の上に止まられたら大変だというので、ハエを見ながらの食事になる。
そんなだから、みんなに嫌われた。男子のほうに行くと、うつるから来るなと蹴飛ばされる。女子のほうに行くとうつるからと逃げられる。徹底的に。
そうされ続けると、いじめられることが心にしみこんで分かったのか、誰の所にも寄り付かなくなった。休み時間になるとどこかへ行ってしまう。どこに行くかというと、校庭の脇にアオギリの木が三本あって、そこに行く。一人でテクテクテクテクと歩いて行って、木にもたれ掛かっている。そうして、いかにいじめられてもやっぱりみんなと遊びたいのか、みんなの遊びを上目遣いで見ているんだそうです。
あんまりいじめられると、鼻のあたりが変になるらしく、しらくもは、いつでも青洟《あおばな》が出ていたそうです。同級生の間ではもう気になってしょうがない。口に入るのじゃないかって。でも口に入りそうになると、頭をひゅっと振ってすすり上げる。そうすると見事に元へ戻る。
椋さんたちは、しらくもが何回すすり上げたら、終業の鐘がなるとか、数えたりしていたそうです。子供というのは案外残酷なことをするんだと。
そんなしらくも君ですが、勉強のほうは一年から六年までずっと一番だった。これもオチがあって、尻から一番。卒業するまで二番と下がらなかったそうです。
その話になったときに、当時83歳の、小学五、六年と担任だった恩師が、椋さんに話しかけてきた。椋さんの手をギュっと握って。そして恩師はこう言いました、
「おれは38年間教員生活をした。その教員生活の中で、しらくもほど始末に困った劣等生に会ったことはなかった。こんな者を相手にしていたら他のものが迷惑するというというので、教室の一番隅に一人だけ並ばせといた。そして、教科書を忘れようが居眠りをしようが、授業時間に漫画を読もうがほったらかしといた。しらくもはなあ、おれの教室にいたというだけで、おれの生徒ではなかった。ところがしらくもは、今、大したやつになっているぞ。おれはしらくものことを考えると、地獄の底まで罪を背負っていかねばならない」
と。そう言ってその恩師は椋さんの手を握ったまま、涙をこぼしました。
その恩師の話の通り、しらくもは、そのころ下伊那・上伊那《かみいな》を通じて、随一といわれる優れた農業指導者になっていました。どういう考えから、あんな知恵が出るのだろうという斬新な方法で、農家を導いていく指導者になっていた。
人間というのは、人生というのは、だからわからない。最後まで生きてみないと。
恩師の38年間の中でどうにもならなかった劣等児が、今では人々から尊敬される農業指導者になる、ということが起こる。
しかし、椋さんはああまでみんなにコケにされた人間が、なぜ人生を転換することができたのだろうか、と不思議に思いました。
そこで二次会に行って、しらくも君とお酒を飲みながらしんみり話した。
椋さんはその時、「君みたいな人がこうした人物になっているとは思わなかったなあ」とつい口をついて出てしまった。これはしらくも君に対して、随分と失礼な言い方です。
しかし人間本当に偉くなると、そんなことは歯牙にもかけない。「うん、みんな、そういうぞ、ハハハ」と言って笑うだけ。
そして椋さんは「君、何か原因があったのか?」と聞きました。しらくも君は「あった」という。
しらくも君は続けました、
「おれはなあ、頭にできものが出来ていたということと、勉強ができなかったということだけで、みんなからバカにされ、のけ者にされた、そして先生からも見捨てられた。悲しかったなあ」
ボーッとしているようで、ちゃんとしらくも君はわかっていた。
「悲しかった。特に朝が悲しかった。朝日が障子戸にバァーと当たってくると、妹や弟は“朝だぁ”といって喜んで飛び起きるが、おれは、神様は何で朝というものをこしらえたんだろうか。今日もまたみんなからいじめられのけ者にされる。そう思うとなかなか起き上がれなかった。いつもおやじに怒られては起きて出た」
「この前もなあ、夕方、学校の前を通ったら、校庭には誰もいない。三本あったアオギリの木は二本枯れて一本だけになっていた。それを見た途端、おれは何か磁石にでも引かれたように、アオギリのほうへ行った。そして木を撫でてみた。木はザラザラとして、おれの六年間の苦しみ・悲しみがいっぱいこもっていると思ったら、思わず泣けてきた。
その時、おれの子供だけにはこんなつらい目をさせまいと思った。だから、子供が本当に勉強したいと言ったら、おれは貧乏だが、牛を売り、田を売り、家を売ってでも、どこまでも学費を出してやろうと思った。しかし、子供はおれの脳みそに似て、いまだに成績は尻から数えたほうが早い、こんな事じゃおれと同じく苦労するなと思っていた。
ところが、高校二年の夏休みの前に、こんな分厚い本を3冊も借りてきた。どんな本かと思ってみたら、カタカナで舌がもつれそうな難しい名前の本だった。こんな本を読む気になってくれたかと、うれしくてうれしくて、久しぶりに毎日仕事に行っていた。ところが、何週間たっても子供は本を読んでいない。本の上にほこりがつもってきたから、読んでないのはすぐわかった。
そこでおれは、これは怒っても駄目だ、この学の無いおれが少しでも読んで、おれより多く学校に行っているお前が読めないのか、お父さん、これ一冊読んだぞ、と励ましてやろうと思って、それを読みだした。人生をかけて読みだしたんだ。最初は難しくてもうやめようかと思っているうちに、おれはその本に感激してなあ、たちまち3回も読み切った」
椋さんは「それはなんていう本よ」と聞くと、「ロマン・ロランという人の、『ジャン・クリストフ』という本だ」という。しらくも君の人生を変えた本です。
「何に感激したの?」と聞くと、「おれの運命が書いてあるんじゃないかと思うほど、人間の苦しみが書いてあった」という。
ベートーベンという大作曲家がいます。耳が聞こえなくなっても作曲を続け、素晴らしい曲をたくさん書き上げた。耳が聞こえなくなるという作曲家として致命的な苦しみ、絶望を味わいながら、大作曲家となったベートーベン。その人間苦を題材にして書かれたのが、『ジャン・クリストフ』という小説です。
ロランには別にベートーベンの伝記がありますが、それではなく、ベートーベンの人生を題材として、フィクションとして書かれたのが、『ジャン・クリストフ』。
だから、そういう異常な苦しみをした人間が、異常な苦しみが書かれた小説を読んだので、それが共鳴しあったのでしょう。
しらくも君は、
「三回読んだ。おれの運命が書かれてあるんじゃないか、と思うほど似ていた、苦しみが。ところが、ただ一つおれと違うところがあった。主人公のジャン・クリストフはどのような苦しみの中に落ち込もうが、絶望の底にいようが、必ず這い上がってくる。彼は苦しみや絶望という言葉を知らないかのように火の如く燃えて生きている。ああ、おれもこういう生き方をしたいと思った」
と、こう言う。
「おれは、しらくもという名の重しの下にずっと今日まで小さくなって生きてきた。この人生を燃えて生きたい、この人生を生きた、という本当の生き方をしてみたい、そう思った。心の底から。そしておれは、何か燃える元を持たなきゃならないとさんざん考えて思った。おれは農家の小せがれだから、農業そのものの中に燃えて生きようと決心した」
それからしらくも君は、農業の専門書を読み始めた。
しかし、農業の専門書というのは、非常に難しい。農学部というのが大学の専攻としてあるぐらいですから、その学問の範囲は多岐に及びます。化学や数学、物理学など。また専門用語のオンパレードで、それを理解する国語力もいる。勉強ができなかったしらくも君どころか、普通の人間だって、とてもじゃないがスラスラ読める人なんていないでしょう。
しかし、しらくも君はあきらめなかった。わからないところが出てくると、本を抱えて村役場の農業専門委員のところに聞きに行く。初めの半年は「よく来た」といって教えてくれた。だが、それからは毎日毎日2度3度行くようになると、職員もうっとうしくなって、彼が来そうな時間になるとトイレに逃げてしまう。ですが、今のような洋式と違い、当時は和式です。あれに30分もしゃがんでいたら、足がしびれて立てなくなる。だから職員が我慢できなくなって出てくると、しらくも君は出てくるまで待っていて、つかまってしまう。
そんなことが続いていると、ついに職員のほうが根負けして、腹をくくって付き合うことにした。ですが、普通なら、それだけ嫌がられたらあきらめます。
ところが苦しみも大きいが、その苦しみを乗り越えようと本気で思った者はちょっとやそっとでは、あきらめない。そうやって学んでいるうちに15冊ぐらい専門書を暗記してしまったそうです。
そうしたら、もう楽にあとはスイスイ読めて、そこから実験したり応用したりしているうちに、しらくも君は人々に指導員と呼ばれるようになったそうです。
自他ともに認める厄介者だった、しらくも君。
そんな自分から苦厄を取り外すのではなく、生きる苦しみ自体を転換することによって、人生を転換していった。今回のテーマである、「度一切苦厄」をまさに体現した生き方です。
私が注目したのは、しらくも君が、大人になって改めてアオギリの木と対面した時です。
しらくも君の苦の象徴だったアオギリ。
最初はアオギリの木を前において眺めるように、自分の苦しみを見ていた。
でもその苦しみは、そうやって眺めているだけだから解決しないと気付いた。
中途半端になっていた心が、そこからうんとはたらきだして、苦しみの元を辿ると、そこに自分自身がいたのだと思います。
そうなると、自分の抱えている苦しみを、丸ごとを救えるのは自分しかいないのです。
だからロランの『ジャン・クリストフ』にも、感激した。彼をして、自分の運命が書いてある、とまで言わせたのだと思います。
それが、彼にとっての、大いなる度一切苦厄だったと、私は見ています。
さて4回にわたって、「度一切苦厄」という語句について、皆さんと考えてきました。
苦厄を度すという表現は、苦は五蘊の生んだものだから、取り外したり消したりはできない。それを解決するならば、人間の心に丸ごと向き合って、五蘊を中途半端なことではなしに、充分にはたらかせることで、解決できる。このことを表現するものとして、苦厄を度すという言い方になる、ということを言ってきました。
また、その度す対象は、あくまでも自分の心であるということを、禾山和尚の問答からも学びました。
そして、それらを総括する話として、椋さんのしらくも君の話をみました。
どうか皆さんも私自身もお互いに、自分の五蘊・心のはたらきを信じて、それをうんとはたらかせる、そんなことを生活の中で心がけていきたいものです。
「度一切苦厄」~厄介者の活かし方~(終わり)