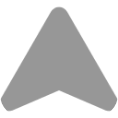般若心経散策(3)

「度一切苦厄」~厄介者の活かし方~第3回
この「般若心経散策」は、『般若心経』の語句を取り上げて、より詳しく見ていくコンテンツです。
第3回は、「度一切苦厄」の、「度」ということを深めていきたいと思います。ここでも、一般的な見方と禅的な見方では、大きな相違が出てくることになります。
禾山無殷《かざんむいん》和尚(中国唐代の禅僧、法系は、石頭希遷―薬山惟儼―道吾円智―石霜慶諸―九峰道虔―禾山)と弟子の問答を見てみましょう。
問う、「古人云く、盲聾喑唖《もうろういんあ》、此の人須《すべから》く救うべし、若し救わずんば仏法に霊験《れいげん》無し。未審《いぶか》し、此の人は如何《いか》んが救われん」。
『祖堂集』巻十二
師云く、「奇特《きどく》の意有りと雖《いえど》も、還《ま》た須く反《か》えって自ら招くべし」。
「学人《がくにん》は則ち甘んじて招かん、未審し、和尚又た如何ん」。
師云く、「山に登れば水脈を知り、室《しつ》に入れば温床《おんしょう》に坐る」。
【訳】
問う、「盲と聾と喑唖と、この三様の人をこそ救わなければならない。もし救うことができないならば仏法に霊験が無いことになる、と古人は言っています。このような人をどのようにして救いましょうか」。
師が言う、「病める人を救おうという、素晴らしく貴い気持ちがあったとしても、まずその病を自分の身に引き受けてみなくてはならない」。
(弟子は言う)「私は喜んでそうなりましょう。さて和尚さんは私をどのようにして救って下さいますか」。
師が言う、「山に登ればちゃんと水脈のあることがわかり、部屋に入ればちゃんと温かいところに坐る」。
ここで病として挙げられている盲・聾・唖とは、実際にそういう障害を持っているということではありません。五蘊を十分にはたかせていないために起こる、苦厄の比喩です。
前回紹介の無文老師の話にも、
「人間が死ぬほど熱烈な愛情を誰かに捧げ得るということは、実に尊いことだ。そうした愛情は宝玉のように大切にしなければならぬ。しかし、人間、たった一人のみを愛して、周囲の愁嘆も迷惑も何も感じないとしたら、どうであろう。その愛は盲目的というほかあるまい」
と、問答中の病の一つである盲が指摘されています。
それは、折角の、人を愛するという立派な心のはたらきを発揮しながら、それが中途半端であるがために苦しむということではないでしょうか。
この問答では、その完全ではない、中途半端なはたらきを、見えない・聞こえない・話せないの盲・聾・唖だと言っています。
その三種の病を救えるか?という問いに、禾山和尚は「救おうと思うならば、自ら招く・自分の身に引き受けるべきだ」と答えます。ここがこの問答の肝です。
自分の身に引き受ける、これをどういう意味に取るか?
弟子は言います、「私は喜んでそうしましょう、ですが和尚は私をどう引きうけるのですか」と。
ここで弟子は、他人の病を自分のこととして見ることだ、と意味を理解しています。
対して、禾山和尚の言う「自ら招く・自分の身に引き受ける」とは、他人の持っている三種の病を自分のこととして引き受けるような間接的なことではなく、まさに自分自身の心の中にある自分の病を直接見出して自ら救え、ということです。
ですから、その後の禾山和尚の言葉、山に登れば水脈がわかり、部屋に入れば温かいところに坐る、というのは、未だ理解してない弟子に対して、
「お前さんも、喜んでそうするというなら、私にどう救うのかと問うのではなく、まず自分の心の病を、山に登ったり部屋に入ったりするように見てみたらどうだ。自分の病を持ちながらそれがわからない、今のお前さんがまさにそうじゃないか」
と言っていることになります。
ですから、五蘊を十分にはたらかせるということは、自身の救いを徹底して行うということに他なりません。自らが度す対象は、自分自身に他ならないのです。
そうして生きることが、それを具《つぶさ》に見ている周りの人々にも、そう気付かせるきっかけになります。
つまり、自分の心は自分で救うしかありませんが、周りの人々にも、そのことを知るための契機となり、それはそれでりっぱな人助けになるのではないでしょうか。
だから五蘊をはたらかせて生きることは、自分の救いと同時に他者の救いとなるといえます。
厄介者をどう活かすかで、まったく人生は違ってきます。
(第4回へ続く)