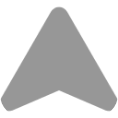石頭希遷 – 禅の名僧(11)

石頭希遷(せきとうきせん / 700~791)
自己という言葉。「ジコチュウ」なんて使われ方も今ではします。
現代の私たちは、自己や個性にこだわった結果、それが行き過ぎて自己や個性に強い執着をも持つようになってしまいました。それは本来の自己とは程遠いものです。
では本来の自己とは何なのか?
今回の名僧は、その自己の向上を絶やすことなく生きた、石頭希遷 (以下、石頭) を取り上げてみます。
出身は端州高要《たんしゅうこうよう》(広東省肇慶市)、姓は陳氏、誕生の際には瑞兆が現れたそうです。
幼いころから静かで普通の子供とは交わらなかったといいます。乳歯が抜け生えかわる頃と記録にはありますから、生え変わり始める7~8歳ぐらいの時でしょうか、母親に連れられてお寺に詣でた際、母親は礼拝した後に「これが仏さまですよ」と言うと、石頭も礼拝し長い間眺めて「これは人です。形や手足は人と何も違いません。仮にもこれが仏なら私も当然なるべきです。」と言いました。すでに石頭は、人の中に仏性があると説く頓悟禅の要点を、幼少の時に掴んでいることになります。
しかし当時、石頭の育った集落では、石頭のこの言葉に耳を傾ける人や理解する人も無く、悪霊の祟りを恐れ、過剰なほど寺社に詣で供え物をして、神仏の助けによって福を得ようという人々がほとんどでした。そこで幼い石頭はその祈禱のための道具を壊し、生贄になっている牛を連れて帰ったりしました。
幼いながらも頓悟禅の要をつかみ、世間に敷衍《ふえん》している宗教観に違和感を感じ取った石頭の、これが最初の布教伝道なのかもしれません。まさに頓悟禅の継承者としてふさわしい少年時代のエピソードです。
またこのエピソードは、石頭が少年時代から俗信にもたやすく迷わされず、自らが正しいと思うことには、それを実行しやり遂げる強い意思を持ち合わせていたことも物語っていると思います。
それから数年を経て、石頭は新州《しんしゅう》(広東省雲浮市新興県)の国恩寺(韶関の南華寺ともあり)の六祖慧能の存在を知ります。新州は石頭のいる端州高要から隣接している場所です。
遂に国恩寺にて、石頭は六祖と相見します。六祖は石頭を一見してその素質を見抜き、自分のもとにやってきたことを喜びました。石頭の頭を撫でて「君は私の仏法をきっと嗣《つ》ぐだろう」といい、沙弥《しゃみ》(少年の僧)として出家をさせて後に羅浮山《らふざん》にて受戒し正式な僧になりました。
六祖の示寂年は713年。石頭の生年は700年。このことから見ても、二人の交流はほんの一時だったのでしょうが、稀代の大禅僧と過ごしたその時間は、石頭には何ものにも代え難いものであったことでしょう。
ほどなく別れの時が来ます。六祖は寂する際「尋思去(思を尋ね去れ)」(『祖堂集』)と言いました。「思」とは人名で、六祖門下の五大禅匠の内の一人・青原行思《せいげんぎょうし》(673~741、以下、青原)のことです。また「尋思去」とは「よく考えなさい」というもう一つの意味もあると言われています。
六祖の指示通り、新州から遥か遠く江西吉州《こうせいきつしゅう》(江西省吉安市)の静居寺《じょうごじ》(浄居寺・靖居寺とも)にある青原を尋ねます。石頭が青原に出会った時、こんな問答がなされたといいます。
青原「どこから来たか?」
石頭「曹渓《そうけい》から来ました。」
青原はそこで和痒子《わようす》(孫の手のようなもの)を取り上げて問うた、
「さて、曹渓には這箇《しゃこ》(これ、このという意味)があったか?」
石頭「曹渓だけではなく、インドにもありません。」青原「それならば、君はインドに行ったにちがいなかろう、そうなのか?」
石頭「もし行っておったら、あることになってしまいます。」
青原「まだ駄目だ、もっと先を言え。」
石頭「和尚さんも半分は言うべきです。希遷(わたくし)ばかりになぜ尋ねるのですか?」
青原「君に言ってもかまわないが、今後きっと誰もうけとめないだろう。」
(『祖堂集』、石井修道氏著『石頭』を参考)
お決まりの問いで始まるこの問答ですが、字面でわかることを聞いているのではなく、問答の主題は悟りに他なりません。曹渓とは六祖が住した曹渓山を指し、また六祖そのものを指します。六祖の元から来たという石頭に対し、青原は和痒子を取り、「そこにはこれがあったか?」と聞きますが、もうこの時点で「これ」というのは悟りを指します。痒いところに手が届く孫の手のように、悟りも人の心の不快を解決するという意味があるでしょう。日用品に悟りを見立て問答するスタイルは頓悟禅のお家芸です。
そうなると、今まで他の名僧伝でも言ってきたように、悟りがあると言ってしまうことは、悟りの否定になってしまいます。とらわれないのが悟りですから、あると言った途端に、あるということにとらわれるからです。だから青原も孫の手を示しながら、問う時にはあえて「これ」というのです。そういうことが分かっている石頭は、青原との問答の中でも決してあるとは言いません。
この問答で青原は石頭の力量を見定め、自分の傍において修行させました。
そうして特別扱いとも取れる待遇で、青原の傍に居ることを許されると、道場の中には不穏な空気が流れ始めました。容姿も優れていたという石頭は、道場の修行僧の噂のタネでしたが、師の青原は「君が正しければそれでいい」として取り合いませんでした。
ある日、朝食の時間に粥が配られた時、食事の係の僧が調べて回っていると、石頭が青原の粥を取って食べているのを見つけました。修行僧達は日頃、青原の石頭への特別扱いを良く思っていなかったこともあって、青原と石頭の両者を激しく誹謗し、石頭の過ちを青原に謝らせました。
その後、青原は石頭に言い聞かせます、「今後断じてこんなことをしてはならない。君がこんなことをしたら、君の正しい眼さえ台無しになってしまう。」と。
この言葉は、粥を食べたことを禁じているのではなく、おいそれと容易く自分の悟りを人に見せてはいけないという意味の言いつけです。師の粥を食べるということは、師と自分は悟りを通じて一体である、ということを石頭は示したつもりなのですが、他の悟っていない者にはそうは見えず、ただ多く食べたいからズルをしたというように映ったのです。少年時代に仏像を見て人だと言ったことや、悪霊を恐れるあまり牛を生贄にして、平安を祈ることを間違いだと言った石頭の性格をも、青原はよく掴んでいたのでしょう。以降の石頭を見ていくと、この青原の言い付けを堅く堅く守っているように思えてなりません。
極めて優秀だけど、一途なその性格が、時にトラブルに巻き込まれる原因にもなり、人の妬みを不用意に買って、石頭の人生が立ち行かなくなることを憂慮した、青原の親心からの苦言と言えるかもしれません。こうして見ると青原・石頭の二人には単なる師弟以上の関係があったと思えてきます。
その関係は石頭が嗣法《しほう》(法を受け嗣ぐこと)する時の問答にもよく表れています。
青原「君はすでに受戒したが、戒律の条文を聴いたか?」
石頭「戒律の条文を聴く必要はありません。」
青原「では、戒を覚えたか?」
石頭「戒を覚える必要はありません。」
青原「君は(南嶽)懐譲和尚の処に行って手紙を届けてくれないか?」
石頭「いいですとも。」
青原「すぐに立って、すぐに戻れ。君がちょっとでも遅れたら、わしには会えんぞ。君がわしに会えんとなると、座床の下の大斧は手に入らぬぞ。」
(石井氏前掲書参考)
問答の途中ですが、すでに戒律についての話題が出てきています。条文を聴くことも覚えることも必要ではないというのは、本当の戒や律は、六祖以来、自らの心にすでに具わっているという思想を元にしています。
また「座床の大斧《ざしょうのだいふ》」とは青原の仏法・禅を意味します。どんな煩悩が来てもその斧で割ってしまう、そしてそれを座席の床に常に携えておくというような意味だと思います。
さて問答の続きを見ていきます。石頭はすぐに出発し、湖南衡山《こうざん》の南嶽懐譲(以下、南嶽)の処へ行って、青原から預かった手紙を渡す前に礼拝して問いました。
石頭「いかなる聖人も慕うことなく、かといって自己の霊妙なる本性をも重んじない場合はどうでしょうか?」
南嶽「あなたの質問は調子が高すぎる。それでは、今後、人は悟れなくなってしまう。」
石頭「むしろ永遠に地獄に沈んだとしても、決していかなる聖人の解脱も求めません。」
(石井氏前掲書参考)
このやり取りは、特に重要な禅の命題を含んでいます。禅ではとどまること、とらわれることを最も嫌います。たとえそれが悟りであっても、です。
石頭の、仏法を否定しているかのような問いにある、「聖人」「自己の霊妙なる本性」という言葉の意味するものは、悟りです。そうなると、石頭がなぜこういった言い方をするのかという真意が見えてきます。
石頭の問いは、悟りとは自己の外に求めるものではなく、自己の中に存在し発見するものだ、という禅で一般的に知られるテーゼ(定立)を成り立たなくするもので、その自己の中にすら存在も発見もするとは言わないということです。そういった定説に凝り固まっていたなら、この時点で石頭の問いにはなすすべもありません。
それに続いて「調子が高すぎる(意訳すると、こりゃまいったな、のような感じ)」と苦言を呈しながらも答えた南嶽の言も石頭と同じことが言えます。「(そんな難しいことを言ったら誰も)悟れなくなる」とは、これも悟りにとどまらないことを、石頭にやりこめられたと思いきや、しっかりと提示しています。
その次の石頭の言も、悟りに到達したとしても、ととどまらないことを、まるで仏法を修めることと逆のような表現で示しています。
石頭と南嶽は、この時仏法や悟りについて、アプローチは違えども同じ見解であることは確認し合ったようですが、とはいえ石頭が南嶽のもとで学ぶには至りませんでした。禅を学ぶには、いくら悟りについて見解が同じでもそれでは足りず、家風《かふう》という一種の相性のようなものが一致しないと難しいといいます。
そんな禅の特徴をこの問答からは垣間見ることができると思います。
石頭は法の継承の機会が南嶽のもとではかなわなかったため、預かった手紙も渡さずに青原のもとに帰ります。ここからまた石頭と青原の問答です。
青原「あちらで信物をもらったか?」
石頭「あちらに信物はありません。」
青原「返書をもらったか?」
石頭「信物ももらえず、手紙も届けていません。」
石頭「わたしが出発する時、和尚様は言われました、〔すぐに戻って、座床の大斧を受け取れ〕と。今、こうして戻っております、どうか大斧を下さい。」
(石井氏前掲書参考)
「信物」は印となる物のこと。これも悟りを意味します。「信物ももらえず、手紙も届けていない」という言は、誰からもらうでもなく、誰かにわたすわけでもなく、自分の中にすでに悟りはある、ということを提示するものです。
それから彼は、青原に座床の大斧を切望します。ここでの青原の役割は、石頭の悟りが本物かどうか見極めるということです。こればかりは石頭も自分ではできません。自らの悟りの見極めは、師である青原に託すしかない。その見極めるということを座床の大斧=青原の仏法としているのでしょう。
この問答の後、青原はしばらく黙っていました。そして、仏法をしっかり守って絶やさないように、との訓戒のような言葉を石頭にかけ、片足を垂れたと言います。それはまさに青原から石頭に座床の大斧が渡された、つまり嗣法《しほう》された瞬間です。
青原のもとに来てすでに20年ほどが経ち、石頭も40歳頃のことでした。
しばらくして師の青原は亡くなります。
3年喪に服して、石頭は長年住んだ江西吉州の静居寺を後にし、新たなる活動の地を目指します。
目指した地は一度行ったことのある湖南の衡山です。南嶽に手紙を届けに行って、渡さずに帰ってくることになったあの地です。
衡山に着くと、そこの南台寺《なんだいじ》というお寺の東にある、台状の岩石の上に、庵を建てて住みました。石頭という号はそこから付いたものです。
衡山は中国古来の霊山で、当時も名僧・傑僧が多く住んだ場所として知られていました。当然石頭がいるという話も徐々に広がります。そしてあの問答をした南嶽の耳にも入ることになります。
南嶽は自分では直接行かず、弟子を使いに行かせ間接的に幾度か問答をしますが、その答えのどれもが、20歳以上も年の離れた老禅匠である南嶽と、堂々と渡り合うような立派なものでした。
南嶽は思わずこう言ったそうです、「あの坊さん、今後、子孫の代に、天下の人の口を閉ざしてしまうだろう」と。
世の中の人はみんな、石頭には歯が立たなくなるだろう、という意味の、予言のような誉め言葉です。
そして石頭はこの南嶽の予言通り、実際に人の口を閉ざしたことがあります。
龐蘊居士《ほうおんこじ》(?~808)という在家の禅者との問答で、居士の「一切の存在と関わりを持たぬ者、それはどういう人でありましょうか?」という問いに対し、石頭は居士の口を手でふさいで閉ざしました。それで居士は悟るところがあったといいます。
この問い、どこかで見たような気がしませんか?そうです、南嶽とあった時、石頭が問うたあの「いかなる聖人も慕うことなく、かといって自己の霊妙なる本性をも重んじない場合はどうでしょうか?」という問いに、感じがよく似ています。
禅はとどまること、とらわれることを嫌います。別の言い方をすれば、措定(措《お》き定める)されることを嫌うとも言えます。一切の存在と関わりを持たないと、措定されることを否定したはずが、それを口に出してしまったら、もとの黙阿弥なのです。関わりを持たないという措定になってしまいます。それでは悟りからは遠のく一方です。だから石頭は居士にこれ以上しゃべらせないようにと、口をふさいでしまったのです。
ですから南嶽が言った、「天下の人の口を閉ざす」というもう一つの意味は、居士との対話にあったようなやり方で、大いに世に禅を広めるだろうということもあると思います。
石頭が湖南衡山にて活躍した同時代、「江西は大寂(馬祖)を主とし、湖南は石頭を主とす。往来憧憧《どうどう》(行ったり来たりするさま)として、二大士に見《まみ》えずんば無知と為す」(『伝灯録』巻六「馬祖道一章」)と称されるように、江西南昌には南嶽の法を嗣《つ》いだ馬祖道一がいました。この二人のもとで、禅は発展を遂げました。
二人は同じ六祖門下の禅の流れを汲みながら、示す禅のスタイルはまるで違いました。だからこそ両雄並び立つことができたと思いますが、そのスタイルとは、ごく簡単に言えば、馬祖が「即心是仏」《そくしんぜぶつ》や「平常心」など、悟りという表現を避けながらも、それを明快に提示したのに対し、石頭はあえて明言を避け、知的理解の限界をさらけ出させるような悟りの提示をしていることです。
自己とは何か?という命題にも、馬祖は、日常のあらゆる場面に自己は現れる、と説くのに対し、石頭は、今まで見てきたように、日常を超越し関わりを持たないという、徹底的に自己の措定を拒否する姿勢を貫きます。
そして今、日本に伝わる禅宗のうち、臨済宗は馬祖の門下から、曹洞宗は石頭の門下から後の時代に生み出されます。
石頭と言えば、あと忘れてはいけないのが、『参同契』《さんどうかい》というお経の著者であることです。臨済宗では読みませんが、曹洞宗では日課経本に出ている良く知られたお経です。衡山の石頭の庵居跡と言われている場所にある大岩には「竺土大仙の心、東西密に相附す。」(インドのブッダの法の核心は達磨から慧可へ違いなく伝わっている)という文句で始まる経文が、朱字で彫ってあります。
その『参同契』の中にも「自ら規矩《きく》(規則のこと)を立すること勿れ」と、自己をとどめない、措定しないことを戒めた一文があります。
唐の貞元6年(791)12月、91歳の長寿を以て、石頭は遷化《せんげ》(亡くなること)しました。かなり後代になって僖宗皇帝《きそう》(唐の18代皇帝)より無際大師《むさいだいし》と勅諡《ちょくし》(皇帝より号を下賜されること)されました。
墓塔は「見相塔」《けんしょうとう》といい、南台寺の2kmほど下にあるという記録は散見されますが、いずれもかなり昔のもの。四度ばかり南台寺を訪れている私も行ったことがありません。2018年に参観した時も行けませんでした。現在衡山には人民解放軍の施設・敷地がありますが、もしかするとそういった立入禁止のエリアに含まれてしまったのかもしれません。また文化大革命にて破却されたのかもしれません。だとしたら残念なことですが、いずれにしても詳細は不明です。