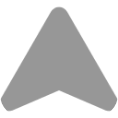今のところは【5】〜不安と安らかさ

この連載は、松本市神宮寺様の寺報『山河』に掲載された禅人代表・山田真隆執筆のテキストを、谷川住職のご協力を得て転載したものです。(今回の記事は2023年・夏号に掲載されたものです)
不安の中で
「止まない雨はない」
私たちを不安から前向きにしてくれる言葉です。
しかし、この裏には、辛いことの後には、必ず幸せが訪れて欲しいという下心があるようにも見えます。
また、雨が降っている今現在をやり過ごして、雨が止むのを待つしかないという意味にも取れ、降っている今をどう生きたらいいのかについては学べません。
「止まない雨はない」、換言すれば「必ず雨は止む」になりますが、天気は刻々と変わるもの。雨が止んで晴れ間が見えても、また雨が降ってきます。その度に私たちは雨が止むまでやり過ごして、晴れ間が来るのを待っているべきなのでしょうか。
それに雨が止んだとしても、それまで降った雨は地面に染み込んで残ります。雨という現象は晴れになったからといって完全に消え去るものではありません。
だから、雨に譬えた私たちの生活の中の不安というものも、人生が好転したとしても消えないものです。
地震という不安
その消えることのない不安の中で生きていることを、時に思い知らされます。
去る5月5日、午後2時42分ごろ、私の住んでいる能登半島の先端・珠洲市を震度六強の地震が襲いました。2階の自室にいた私は、揺れが続く中で、いつ部屋を出ようかとまごついている間に、立っていられない揺れになってしまい、その場に座り込むしかなく、建物が崩れてきたらその時は終わりだなということも頭をよぎりました。
数十秒は揺れていました。大体揺れがおさまって部屋を見ると、いろんなものが散乱していました。
そこから寺の被害の様子もある程度想像出来ました。すぐに1階に降りて、在宅している家族に声をかけてまわり、寺の損傷の具合も見て回りました。それは明らかに去年の被害よりも大きいものでした。建物は倒壊こそないものの、木組は外れ、位牌や燭台のような背の高いものは倒れて転がり、崩れた壁や天井から落ちてきた土砂で足の踏み場はありません。
とりあえず、生活に直接関係のない本堂などは後回しにし、居間や台所の片づけをしました。
そうやってなんとか一息ついていたその日の夜10時ごろ、今度は震度五強の揺れが来ました。昼に片付けたものが再び散乱、これには怖いと同時にあきらめの気が起こりました。
その日はもう片付けする気力もなく、散らかったまま床に就きましたが、余震も頻繁に続いたのでなかなか眠ることもできず、一夜を過ごしました。
求心歇む処即ち無事
たまたま今回は私のところに地震が来ましたが、日本に住んでいる限り、地震は免れないといいます。また降りかかる災難は地震だけではありません。数え上げたらきりがないほどの、災難の起こる可能性のある中を、私たちは生きています。
災難の「災」という字は中心に「人」がいます。これは地震のような天災でも、人間の心掛け一つで本当の災いになってしまう恐れがあることを示唆するものではないかと、私は考えます。実際、現在珠洲では地震の後、家屋の修復業を偽った詐欺まがいのことをする一団が都市部から流れ込み、被害が横行するのを聞くようになりました。このように、天災のかたわら人災にしてしまうこともあります。
臨済宗の宗祖・臨済禅師が生きた時代も、不安と否応無しに付き合わされる時代でした。政治は腐敗し、犯罪は横行、もう朝廷に民衆を統治する力はなく、代わりに地方に力を得た豪族たちが、覇を唱える群雄割拠の戦乱の時代が、臨済禅師の時代です。
そんな中で臨済禅師が説いた教えに「求心歇む処即ち無事《ぐしんやむところすなわちぶじ》」があります。
人間は常に安らかさを欲求します。でもそれは求めれば求めるほど、自分が安らかでないこと・不安であることを吹聴するようなものです。だからそれをとめることが、安らかさへの方法だという教えです。
また、「やむ」とは、それまで続いていた状態がとまることをいいます。たとえば雨がやむということは、降ってくる雨が止まっただけで、それまで地面に降った雨が消えて無くなることはありません。
同じように、安らかさを求めて、かえって不安になっていた、それまでの生き方を否定するということではありません。 一旦雨が止んだとしても、晴れの日もずっと続くことがないように、一つの心配事が解決したら、また別の心配事と向き合わなければならないというのが、私たちの日常です。
だから、臨済禅師の教えは、もし間違った生き方をしても、決して否定せず、その都度雨がやむようにそこから何度でもやり直せばいいという、やさしい教えです。
隣り合わせの不安と安らかさ
詩人の苗村(なむら)吉昭さんは、自著で「人生で一番打ちのめされたこと」として、お子さんが、「まともな部分は心肺機能だけ」という程の重度の重複障害を持って生まれてきたことを挙げています。
最先端の大学病院に設置されているNICU(新生児集中治療室)でも、治療といっても根本的に障害を治すことは出来ず、延命措置のみの治療を余儀なくされ、我が子と自分の行く末にとてつもない不安を抱えてしまっていました。
とにかく苗村さんは、障害をもって生まれてきた我が子の生きる意味をどうしても見出したくて、いろいろな障害児施設を見て廻りました。
そこには障害児を持った親の責任を認識するよう迫る人や、障害を個性として認識せよと説く人もいました。ですが、苗村さんは我が子の生きている意味、命の意味を納得することがなかなかできませんでした。
三月のある日、NICUに面会に行った苗村さんは、他の木はまだ花をつけていない中、NICUの大きなガラス窓の前だけは、なぜかサクラの花が満開になっていることに気が付きます。
看護師さんが、近くのボイラー室の温風でNICUの前だけはいつも早くサクラの花が咲くのだと説明してくれましたが、自分の子供を抱いて満開のサクラの花を眺めながら、苗村さんは「違う」と思いました。
このサクラの花はこの子の命の姿であり、ここにいる新生児たちの命の熱気を受けて早く咲いているに違いない、と確信したといいます。
社会的には何の役にも立たない命かも知れないが、このサクラの花に我が子の命が現れているのだ、と苗村さんは初めて自分の子供が生きている意味を納得できました。
我が子が重度の障害をもって生まれてきたというのは、苗村さんにとって予期せぬ災い、まさに地震のようなものでしょう。そして決して快方に向かわない障害を持った息子さんという不安を前に、苗村さんもどうにかしてその不安を取り除こうとしました。
つまり、息子さんの生きる意味を求めることで、安らかさを求めていたのだと思います。そんな求めて止まない安らかさが、求めることをやんだところに発見できるというのは、実は常に安らかさは私たちの傍らにあることの証ではないでしょうか。
私たちは不安とも隣り合わせですが、同じく安らかさとも隣り合わせなのです。