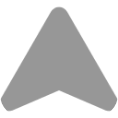灯りの真実

先月に引き続き、灯りをテーマに書いてみたい。
一言で灯りと言うが、その実《じつ》は二つの要素が合わさっているものである。
灯有れば即ち光《かがや》く。灯無ければ光かず。
『六祖壇経』
灯は是れ光の体《たい》(本体のこと)、光は是れ灯の用《ゆう》(はたらきのこと)なり。
名は二有りと雖《いえど》も、体は本《も》と同一なり。
語録にもこのように灯りの二つの要素の説明がされている。
二つの要素である体と用とは、人で言えば体《からだ》があって、その体を使っていろんなはたらきをすることを示している。
どんな灯りでも、灯した時には辺りを照らす。灯りとは、本体である灯っている光と、その光が照らすはたらきという二つの要素が、同時に起こっている状態なのである。
そしてこの説明は、語録に収録されていることからわかるように、灯りに喩えた人の心の説明である。
特に人の心の「禅定」《ぜんじょう》ということを灯りという本体に、「智慧」《ちえ》ということを灯りが照らすはたらきに、それぞれ喩えている。
禅定とは、普通は心を落ち着け鎮めることを言うが、ロウソクの灯りはよく見ると落ち着いてなどいない。むしろ揺らめいてひと時も動きを止めない。あるいは蛍光灯の灯りも、人間が認識できないスピードで明滅を繰り返しているという。これも刹那も動きを落ち着かせることはない。
つまり、灯りに禅定を喩えることは、単に落ち着け鎮めるということを意味するものではないのである。
禅の教えとしての禅定とは、灯りが揺らめくように、常に姿形を変え、とどまることがないことを示すものなのである。
本体がそうだからこそ、智慧の照らすはたらきも、とどまることなくすべてを明るく照らす。今まで見えなかった、気づかなかったことを、見たり気づいたりする心のはたらきが智慧である。智慧を駆使すれば、照らすはたらきによって、あらゆるものが私たちの眼前に現れる。
灯りが明かりである時の明るさには
「夜の道」上山範子・吉野弘合作
気づかず通り過ぎてきたわたしが
今初めて消えかかる街灯を見上げている
わたしが、もしひとつの灯りであるならば
その点滅にいち早く気づくのは
多分、わたしではなく
わたしの灯りを、それまで知らずに受けてくれた者
わたしは、ひそかに思い描く
点滅し始めたわたしを、息つめて見つめている者の
眼差し
この詩の「わたし」の見ている灯りは街灯である。そしてそれは消えかかったために、初めてわたしの気づくところとなった。気づいたわたしの前に現れた、いつも見ているが今は違って見える街灯。
わたしは想いを馳せる、もしこの灯りがわたし自身だったら、と。
詩はいう、点滅し始め、消えかかって初めて自らの灯りに気づく、と。
また気づくのは自分ではなく、その灯りを知らずに受けてくれた者だとも。
それでは遅いようにも、救いが無いようにも感じるが、決してそんなことはない。
わたしが気づこうが気づくまいが、わたしの心の灯りは、ひと時も動きを止めず、自分を照らし続けてきたのである。
だからその灯りを受けてきたのも、他ならぬわたし自身なのである。それならば灯りに気づくのは、当然わたしである。
灯りは、元より人の心に灯って、そして自らを照らす。
誰一人として、その灯りを持っていない人はいない。