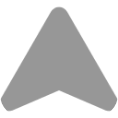灯りという功罪

ブッダ晩年の教えにも「自灯明《じとうみょう》」があるように、灯りというのは悟りの比喩としてよく使われるものである。
真っ暗な闇の中にともす一点の灯り、それがたとえわずかな範囲しか照らさないとしても、その灯りがあるとないとでは人の生活は大きく違ってくる。かつて人は灯りを見て、その可能性を見たことだろう。やがて精神世界が発達して宗教が生まれた時も、人の心の理想を灯りに見立てたであろうことは、容易に想像がつく。
禅宗でも、祖師方の悟りの系譜を、「伝灯《でんとう》」、「法灯《ほうとう》」などと呼んでいる。灯りを悟りに見立てる話で一風変わったものが「久響龍潭《きゅうきょうりょうたん》」(『無門関』第28則)だろう。
徳山《とくさん》という僧が、後に師となる龍潭《りょうたん》という僧に会いに行き、話し込んでいるうちにすっかり夜も更けてしまった。「さあ、あんたもう帰りなさい。そして明日また来なさい。」とばかりに龍潭は徳山を玄関まで送りだした。
徳山も一度外に出てみたが、外は真っ暗闇である。どこを歩いたらいいかわからない。そこで龍潭は、粗末なロウソクのようなものを持って来た。火のついたそれを徳山に渡そうとしたその時、龍潭は灯りを吹き消した。その途端、徳山は悟ったという。
「伝灯」などと言う手前、灯りとは手渡しして伝えていくものとばかり思っていると、こんな話があるのである。灯りを渡すどころか、渡そうという時に吹き消す。そして相手もその意味を理解して悟る。
つまり、灯りとは、自分で自分の心に、人知れず灯すものなのである。人から受け取ったり、人に点けてもらったりするようなものではない。そして灯したとしても、決して人に見せびらかすようなものでもない。
本コラムには以前にも登場した、私の敬愛する詩人・吉野弘氏の「Candle’s Scandal」《キャンドルズ スキャンダル》という詩の本意も、灯りというものの持つ一種の万能感からくる自己陶酔を、ユニークな文体で厳しく戒めているようである。
誰かが私を作って下さった
《「Candle’s Scandal」吉野弘》
蝋を練り固めて。
使命感まで入念に吹き込んで下さった
世の中の光になれ-と。
その気になって私は
私を光に変えつづけている
焔に食われながら。
私を焔に食わせるのは身の因果と諦めるにしても
気色が悪いのは焔の君。
ご自分が光なので
まわりをすべて
闇にお見立て遊ばすのだ。
たとえば昼日中の明るさの中で灯されても
“まわりが暗い”と、じくじく託《かこ》ち遊ばす。
世の光などという運命を負わされて生きておいでになると/
陽のある普通の明るさまで
お気に召さなくなるらしい。
闇の中に進み出られるときは
はしたないほどの喜びよう。
背すじを伸ばし
青白いような赤いようなほそい舌先をゆらめかせて
闇をお説教しにかかられる。
舌が身を食いつぶすという
世の習いも
とんとご存じなくて。
タイトルを訳せば、「ロウソクの醜聞」というこれもユニークなものである。人間が陥りやすそうな心理状態を、このようにロウソクを比喩にして一編の詩を編むという、吉野氏の離れ業にいつもながら感心する。
畢竟《ひっきょう》、人間が使う限り、灯りというものも、人間がどう使うかでその功罪が分かれるのである。この詩にあるようなロウソクの灯りであれば、いくら灯りでもそれは罪である。
そして、龍潭も徳山も灯りの使い方を誤ることはなかった。
そういうたくさんの祖師方が人知れず灯しながら、伝えずして伝えてきた灯り。現在においても、小なりといえどこの禅人がそれに寄与できるように微力を尽くしたいものである。