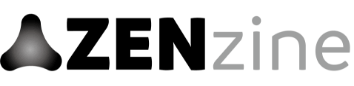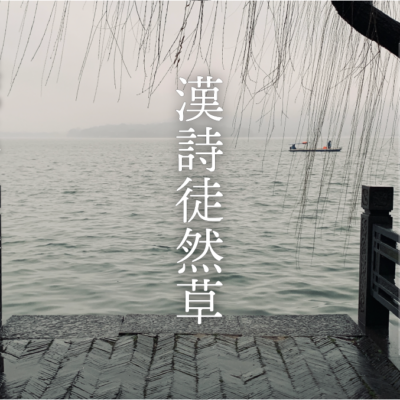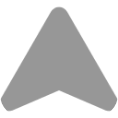『坐禅和讃』私考

先月掲載コラムの“「ガラス」と悟り”で『坐禅和讃』を出した。言い足りないことがあったので、少しまた触れてみることにする。
衆生本来仏なり 水と氷の如くにて 水を離れて氷なく 衆生の外に仏なし
この冒頭の文句、巷間説かれるときは、仏とは水のように自由に形を変える柔軟性を持ち生命を養うもの、反対に迷える衆生とは氷のように冷たく固く形を変えず生命を奪うものとされる。 そして氷も解ければ水になるのだから、氷のような衆生であっても、本来は水のような仏なのだと説明される場合が多いだろう。
水と氷の譬《たと》えは、この『坐禅和讃』だけに見られるものではなく、古来よく見られるものである。ただ、この伝統的な解釈に疑問を投げかけた人がいる。詩人の吉野弘氏である。
〔中略〕
もう一つ
水と氷の譬えで忘れがたいのが『白隠禅師坐禅和讃』冒頭の次の言葉
〈衆生本来仏なり 水と氷の如くにて 水を離れて氷なく 衆生の外に仏なし〉
〈衆生〉は、迷いの世界にある者
〈仏〉はこの場合、悟りを得た者のことだが
水が氷になるように
衆生が仏になる可能性を指し示す
この譬えの絶妙なこと
-それにしても、だ
弟子が師を超えるにも衆生が仏になるためにも
必要なのは寒気。「氷肌玉骨(ひょうきぎょっこつ、美しい女性の喩え)」の美人と近づきになるためにさえ
必要なのが勇気ではなく寒気とは!
まるで氷河期
地球温暖化が
急速に進んでいる御時世だというのに・・・
「氷よ 氷」吉野弘
『坐禅和讃』が取り上げられている詩を、私は他に知らない。一般的にはどちらかと言えばマイナーな部類の『坐禅和讃』が、取り上げられているだけでも驚きなのに、そこに込められた内容たるや、また驚きである。
ここでは、吉野氏は衆生が仏となることを、氷が水になるのではなく、水が氷になることだと指摘し、そのために必要なのは寒気だと言っている。従来の説と水と氷の位置関係が逆転している。
なぜこうなるのか。それは吉野氏が、ひとえに文字に人一倍敏感な感覚を持つ詩人だからだろう。
『坐禅和讃』の文章の文字の並びをつぶさに見ていくと、水と氷の文字の並びに、衆生と仏を対応させると、吉野氏の主張となる。つまり水が衆生で、氷が仏となるのである。
こういった指摘をするのが、初っ端から水が仏だと決め込んでいる宗教者ではなく、専門外の詩人であるところが興味深い。
仏の持つはたらきとは何か?を考えると、確かに水のような柔らかくやさしく、生命を養う穏やかなイメージが先立つが、一方で迷いや妄念を奪い去るという厳格なはたらきもあるはずだ。生命を奪う氷や寒気というのは、そういう厳しい一面を表したものだといえる。心にも氷河期は必要なのだ。
となると、仏というのは、水だけではなく、氷だけでもなく、水と氷の両方をもって仏と見ることも出来る。 頓悟的な見方からすると、そちらの方が理に適っている。
そして『坐禅和讃』の締めくくりは「この身即ち仏なり」である。
冒頭の衆生というマクロ的な視点が、この身という一個人の視点までクローズアップされた上で、仏だと断定される。
始めはぼんやりとしたイメージが、終わりになって私たち一人ひとりの命題としてくっきりと示される。
それが、水であっても氷であっても仏ということ。衆生本来仏であり、この身即ち仏である。
こうまで示してあっても、水と氷、衆生と仏を、私たちはいつの間にか「分かった」つもりで分けてしまっている。
自らの省も兼ねて、ここに記しておきたい。