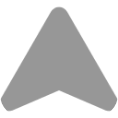「心配」から考える禅の教え

山本玄峰《やまもとげんぽう》老師は、明治から昭和初期を生きた禅僧です。第二十一代臨済宗妙心寺派の管長や静岡、三島の龍澤寺《りゅうたくじ》住職などを務められ、数多くの逸話を残しています。
若くして病気によりほぼ失明というたいへんな困難に直面しますが、病気平癒を願って四国八十八カ所の霊場巡りを始めます。七回目の四国遍路の途中、三十三番札所である高知の雪蹊寺で行き倒れとなってしまったところを山本太玄和尚に助けられ、これが禅僧への道を志す契機となりました。
さて、この山本玄峰老師の言葉に次のようなものがあります。
「心痛はしてはならぬ。だが、心配は大いにせよ」
ここで言う「心痛」、心を痛めるというのは苦しみや困難を抱える人を思いやらずにはいられない慈悲のこころの表れではありますが、あくまで自分の中のみで湧き起こり、自分の中で完結する慈悲のこころであるとも言えます。
もちろん慈悲のこころを起こすこと、それ自体がたいへん尊いことではありますが、もう一歩踏み込んで、頭を働かせて、その慈悲のこころを細かく砕いて皆に分け与える「心配」という行為がよりいっそう尊いのだということです。
心配は「こころくばり」とも読めます。普通に使う心配というのは、心痛の意味合いが強いのではないかと想像します。もちろん心痛するのが悪いということではありませんが、もう一歩踏み込んでみると、これが禅の教えに繋がってくるというのが面白いところです。
例えば、お釈迦様は「応病与薬《おうびょうよやく》」という教えを説かれました。医者が病人の症状に応じて薬を処方していくように、一人一人の苦しみに応じて教えを説くことが必要であるというたとえです。
人々の病気を治す薬も飲む量を間違えれば効果を為さなかったり、逆に毒として作用することさえあります。本当に効果的な薬を患者に処方しようと思うと、医者が患者のことをしっかり観察することが大事です。この「観察」という言葉は、現代の日本語にもなっていますが、本来の仏教用語としては「観察《かんざつ》」といい、ほとけの眼で物事を正しく見極めるという智慧の働きを意味しています。
慈悲の心を届けるためには相手をよく観察し、相手の心と溶け合って調和するように智慧を働かせなければなりません。だからこそ山本玄峰老師はこの心配という行いを大いにせよ、と言われたのです。
修行道場にお世話になって二年目の頃、入門したばかりの後輩の修行をサポートする立場となりました。私はなるべく後輩が叱られる事が無いように先回りをして世話を焼いたり、時には後輩がするべき仕事を先に済ませていたりなどしていました。
今考えると世話の焼き過ぎであったというのは明らかです。とある日に先輩に呼び止められて、「あんたは後輩らの修行が終わるまで、ずっとそうやって世話を焼き続けるのか?」と言われてハッとさせられました。私は結果として知らず知らずのうちに後輩が学ぶ機会を奪っていたのだ、と恥ずかしい思いがしたことを鮮明に覚えています。
私が後輩の事を心配していたというのは紛れもなく本心からではありますが、本当の意味で後輩たちが独り立ちできるように頑張って欲しいというところまでは考えが至っていなかったのです。
「心痛はしてはならぬ。だが、心配は大いにせよ」
当時の私は「心痛」止まりで、まだ「心配」には至っていませんでした。「サポートする立場」にうぬぼれて、後輩をしっかり観察すること無く、目の前のことだけなんとかなっていればそれで良い、という思いでは本当の心配とは言えません。誰かに思いを傾けるというのは、同時に自分のありようも問われているのだと、その時に学ばせていただきました。
山本玄峰老師の言う「心配」というのは単なる自分の思いの押しつけではありません。相手のことを懸命に観察し、行動に移していくというプロセスを通して自分自身のこころのありようにも関わる修行です。
これは修行道場の中だけの話ではなく、私たちの普段の生活の中でも同じことでしょう。日ごろから自分自身を律して、その上で周りに慈悲のこころを傾けていく。それがまた巡り巡って自らのこころを調えていくことに繋がっていくというのが、禅の教えの説く「心配」なのです。