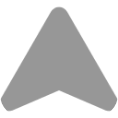コロナ隔離生活の中の自由

コロナウィルス陽性
妻から「陽性だった」と電話をもらった。最初にコロナウィルス感染症陽性と判明したのは次男だった。
ゴールデンウイークが明けて長野県内でも感染者数が多い時期と重なっていた。今なお(令和4年6月現在)、毎日ニュースで県内の感染者数、松本市の感染者数が発表されているが、自分の子どもがその数字の中の一人に含まれることになるとは。ありえないことではないと想定していたとはいえ、電話越しには焦りと不安があった。
感染判明当初は戸惑うばかりであった。保健所の指示を仰ぎ、濃厚接触者となった家族全員がPCR検査を受けた。検査の結果が出るまでの数日間は気が気ではなかった。案の定、妻と子どもは陽性。奇しくもわたしは陰性という判定だったが、念のため一週間の自主隔離となった。
わたしだけかろうじて感染を逃れることができた。なぜわたしだけ陰性だったのかは分からない。「たまたま」県外へ出かけていたこと、「たまたま」夜まで仕事があったこと、「たまたま」すぐに家族と離れてお寺で暮らせる環境にあったこと。そんな「たまたま」が重なったのだろうか。
わたしは偶然陰性だったがこの先も罹患しないとは限らない。妻と子どもは二週間もの隔離生活を余儀なくされ、満足に遊ぶことができない子どもたちはストレスも多かった。大人が考えているよりも、子どもにとってコロナウィルスという目に見えない物への強迫観念はすさまじいものがあった。
わたしたちの自由
『禅ヒッピー』という小説がある。カウンター・カルチャーを代表する作家、ジャック・ケルアックの著作である。彼の代表作「路上」とともに大学生時代に読んだまま本棚にしまわれていたものを、この隔離期間中に引っ張り出してきた。
ジャック・ケルアックといえば、あの鈴木大拙との逸話がある。二人がニューヨークで対面した時、大拙はケルアックに対して、「君たちは自由をはき違えている」と言ったという。大拙は「肘は外に曲がらない。肘が外に曲がったら痛い。肘は外に曲がらないから自由なのだ」と喩え、ケルアックはその真意を理解した。
もし、肘が外に曲がったらどうなるか?それが自由だと言えるだろうか?間違いなく痛いことだけはわかる。
当時のアメリカのカウンター・カルチャーはベトナム戦争への反対や環境破壊への抗議など、自分たちを取り巻く社会への反発であり、そんな社会からの自由を得るための活動だったのだろう。
しかし、この時代を見た大拙は「君たちは自由をはき違えている」と言った。社会や制度から離れよう離れようと自由になろうとして、むしろ社会や制度、活動に惑わされ、縛られている——大拙の目にはそう見えたに違いない。
「自由」はその字のごとく、「自」が主になっている。抑圧も牽制もなにもない、「自《おのずか》ら」または「自《みずか》ら」出てくるので、他から手の出しようのないとの義である。
『東洋的な見方』鈴木大拙
肘は外に曲がらない。そんな不自由な中で見出す自由が本当の自由なのだとケルアックに伝えたかったのだろう。
わたしのコロナ隔離生活
一週間、八畳の庫裡《くり》(お寺の中の居住のための建物)の屋根裏部屋で生活をした。朝はほととぎすの鳴き声で目が覚める。朝の五時の鐘だけが唯一外に出られる機会。早朝の鐘をつくのがこれほど嬉しかったことはない。ゴーンという鐘の音がいつもより身に染みる。あまり動かないので、お腹もすかない。いつものように一日三食食べなくてもよかった。電話はいつも通りかかってくるが法事などのお勤めがなくなった。
空いた時間はどうするか?本を読んだり、原稿を書いてみた。今まで目に留まらなかった詩にも出会うことができた。また、散らかっている部屋を片付け、資料を整理することもできた。家族とは離れて暮らしているので、お互いお寺と家にいながら電話で会話をする。普段は業務連絡だけの電話だが、この時ばかりは声が聴けるだけで嬉しかった。
こんな隔離生活を送っていた。言い方は不適切かもしれないが、家族がコロナウイルスに感染したから、わたしはコロナ禍で自由を体験することができた。外へ出ることができない、人と出会えない、そんな制限はあるが、わたしは確かに自由だった。鈴木大拙の語る「自由」には達してはいないかもしれないが、自由への一歩を踏み出した気がする。
「道をそれて」ゲーリー・スナイダー
ケルアックの著書、『禅ヒッピー』の主人公は実在する人物がモデルとなっている。ゲーリー・スナイダーというアメリカの詩人だ。『亀の島』という詩集でピュリッツアー賞を受賞した彼は、なんと日本の禅寺で長い間修行をしている。京都の大徳寺管長・小田雪窓老師に参禅し、亡くなるまで側にいたという。アメリカから日本へ渡り修行僧と共に生活したこと、禅という生き方を直接体験したことが彼の詩やエッセイには生き生きと表れている。
詩集を繰り出して読んでいると一編の詩に目に留まった。コロナ禍で勇気をもらった詩だ。長い詩だが是非、全文を掲載したい。ここまでの文章を読まなくても、この詩だけは多くの方の目に留まることを願って。
道をそれて
キャロルに
ぼくらは 岩場の上——木立をぬけて何処に道を見つけてもよかった
道なんて全くないところに。
山の稜線と森とがぼくらの目と足の前にその姿を現す
そして昔学んだ行動の知恵が指し示すまま
野生がぼくらを導くに任せる。
ぼくらは前にもここへ来たことがある。
行く道が決まってるところを歩くより
このほうが なんとなくもっと懐かしい、
どんな道だって可能性はある、それに大抵の道は通れる。
途中で行き止まりになっても、それはそれなりに面白い。
通り抜けられたらすごくうれしい、道草や迂回をすれば丸太や
花がみんな見える
鹿の道は真っすぐ上がり、横切るのはリスの道、
床岩を辿って歩を進める。
倒れ木の幹に座って一休み、
岩底に降り立ったり、斜面に沿って曲がったり、観察したり
どちらも選択しているのだ——今は道を分かっても——
後でまた再び出会う、ぼくは正しい、君も正しい
ぼくらは 一緒に出てくる。
マッタケ「松のキノコ」が切り株の根方で 呼吸している。
アカマツの葉と小枝を散りばめて
厚い絨毯を敷いた地面。こいつは すごい!
ぼくらは笑う。確かにすごい。
なぜならどの場所も 他よりすぐれているということはないからだ、
すべての場所はそれぞれ 完璧なのだ、
そして僕らの踵、膝、肩、そして腰は、
みんなその場所を心得ている。
『老子』がどう言っていたか
思い出してみるがいい。道が大事なのではない。
どの道を行っても 行きたい所へは行けないだろう。
ぼくらは 道を大きくそれてしまった。
君とぼく、そしてぼくらは二人とも
それを選んだ!僕らの年来の野外の旅は、
この二人でする散歩の 予行演習だったのだ、
山中深く
二人並んで 岩を越え、森に分け入っていくこの散歩の。
『ノーネイチャー〜ゲーリー・スナイダー・コレクション〈3〉』ゲーリー・スナイダー著 金関寿夫・加藤幸子訳
題名に添えられたキャロルとは、スナイダーの妻の名前である。何回も繰り返し繰り返し読んでいると情景が浮かんでくる。目の前にはたくさんの道がある。通りやすい道、通りにくい道、行き止まりの道、登り道。歩く道を選ぶことが大切なのではない。歩くことが大切なのだ。わたしにはゲーリー・スナイダーの詩には、鈴木大拙の言う自由が感じられる。生き生きとして、軽快で、曇りもないそんな姿が目に浮かぶ。