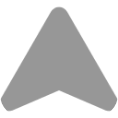黄檗希運 – 禅の名僧(6)

黄檗希運(おうばくきうん / ?-860)
中国では度々大規模な廃仏運動が起こります。
その中で最後の廃仏運動が「会昌《かいしょう》の廃仏」(842-846)といわれるものです。
廃仏運動が起こる理由は、労働をしないことや出家をすることでその家が廃れてしまうことなどが、儒教を精神文化の主柱とする中国ではどうにも受け入れ難かったからです。
しかし中国の祖師方はその困難を、幾多の工夫で乗り越えてきました。
今回はそんな廃仏運動の最中に生きた禅僧を取り上げます。
時代は晩唐、王朝の統治能力が低下し、世の中は犯罪、飢饉、戦争といった社会不安が日に日に弥増《いやま》す時代、黄檗希運《おうばくきうん》(以下、黄檗)が生きた時代です。
生まれは福建省。身長七尺の堂々たる体躯、額には礼拝を多くしたことによる肉腫、いわゆる礼拝だこがあった、と伝わります。
福州の黄檗山にて出家。最初は浙江省の天台山にて学び、その後、百丈懐海に参じて法を嗣《つ》ぎ、当時の宰相・裵休《はいきゅう》の請に応じて江西の黄檗寺(故郷の黄檗山を懐かしんで命名)に住しました。この裵休は、黄檗の語録『伝心法要』をまとめた人物としても知られ、黄檗と縁の深い人物です。
ちなみに黄檗とは日本でいうキハダの木のこと、黄檗寺に住したため、禅僧としての号も黄檗となりました。
黄檗が百丈のもとを出て行脚の途中で塩官斉安《えんがんさいあん》禅師の下にいた時のこと。そこにはまた、後に会昌の廃仏を起こす張本人、十五代皇帝・武宗の不興を買って粛清されかけた大中天子(のちの十六代皇帝・宣宗)もいました。
礼拝をひたすら続ける黄檗を見て大中天子は「何を求めて礼拝するのだ?」と聞くと「ただこのように礼拝しているのだ」と答えます。大中天子は食い下がり「ただ礼拝しているのでは意味がないではないか」というと、黄檗は天子の横面を張ったという豪快なエピソードもあります。
黄檗の禅のスタイルは、「本来無一物」を体現した六祖以来、「平常心」と説いた馬祖、「独坐大雄峰」と標榜した百丈と続いてきた頓悟禅《とんごぜん》を発展させ、日常の中に徹底して仏法を見出そうとするもの。頓悟・頓に悟ることとは、段々と改善していった先に悟り・真理があるというものではなく、畢竟今の日常そのものを認めて肯定していくことです。
礼拝だこがあったと伝わるのも、頓悟禅の体現者として礼拝という日常の行を人一倍重んじ、行っていたことを物語るものではないでしょうか。
黄檗はそんな禅のスタイルによって、門下に臨済義玄(以下、臨済)を打出しました。
臨済の語録『臨済録』には、その際の経緯が書かれています。
黄檗寺に来て3年、臨済は首座《しゅそ》(修行僧のリーダー)に黄檗への参禅を奨められ、仏法とは何かを問いました。その問いが終わらないうちに、黄檗は臨済を棒で打ちました。訳がわからない臨済はもう二度黄檗に同じ問いを発しましたが、都合その三度とも打たれたのです。
こういうところが禅の面白いところ。これは、質問が間違っているから打たれたのではありません。では何が間違っているのかというと、問うこと自体が間違いなのです。
黄檗が臨済を打ったのは、「お前さん自身がそのまま仏法なのだ」と示しているにほかなりません。
自身に仏法がすでに具わっているのであれば問う必要はないでしょう。それは臨済だけでなく私たちも同じです。以前に黄檗が大中天子の顔を張ったのも同じ理由からです。
ですが、それが解らないうちは問い続け、答えを求めていくしかありません。よく、「たたき起こす」という言葉の表現がありますが、まさに黄檗は臨済の心の中にある仏法をたたき起こそうとしたと言えます。
そんな教えになったのは、冒頭にも書いたように、晩唐の困難な時代ゆえに「頼れるのは自分のみ」という社会風潮の影響も大きいと考えられます。
兎も角、黄檗は自身のスタイルでもって、臨済を導こうとしましたが、しかし打つ方に禅があっても、打たれる方に禅がわからなければ通じません。この時の二人の交渉は一方通行で終わってしまいます。
その後、高安大愚《こうあんたいぐ》という僧との機縁を通じて、臨済は大悟への契機を得ますが、大愚はあくまで、お前さんの師は黄檗だと主張したため、臨済は黄檗を再訪し、その法を嗣ぐことになります。禅者・臨済の誕生の時です。
臨済が黄檗の元を去る時、黄檗は、師である百丈から受け継いだ禅板・几案《ぜんばん・きあん》(どちらも坐禅の時に身体を支える道具)を譲ろうとします。即座に臨済は「そんな物要らない」と燃やそうとします。黄檗は「まあまあそう言わずに持って行け、役に立つこともあるぞ」、とまだ若く血気盛んな臨済をたしなめ、持っていかせます。
この後、臨済は北へ向かい黄檗と会うことはありませんでした。
『臨済録』に収録されている二人の今生の別れのシーンです。
黄檗は臨済を見送った後も、この黄檗寺にしばらく住し、のち鐘陵《しょうりょう》(江西省)の竜興寺、宛陵《えんりょう》(安徽省)の開元寺に歴住し、生涯を終えます。生没年ははっきりとはしていませんが、大中年間(847~860)と言われています。断際禅師《だんさいぜんじ》と諡号《しごう》されました。
二人の濃厚な仏法交流の場であった江西省宜豊《ぎほう》にある黄檗寺。
今まで私は四度訪れていますが、最近では2017年に行きました。
江西省の省都・南昌市から東南方向に車で2〜3時間走ると、山の斜面の山林を切り開いたような割と開けた土地が現れます。『臨済録』にも黄檗山での修行僧の数を「七百衆」とあることから、最盛期はここにかなりたくさんの人が修行していたことを伺わせます。
建てられてからそんなに経っていませんが、大分くたびれている感じの、レンガ造りの小さなお堂が現在の大雄宝殿《だいゆうほうでん》(中国のお寺の本堂)となっています。目立った建物はそれのみです。不世出の禅僧・黄檗の遺構としては、少し物足りない気もします。
境内には黄檗禅師が飼っていたトラが水を飲んだという虎跑泉《こほうせん》という井戸もあり、その水も飲むことが出来ます。私も飲みましたが、少し甘い味がしたような気がしました。
その黄檗寺から車で数分走ったところに、黄檗禅師の墓塔があります。地元の牛の放牧場になっているのか、地面には牛のフンがありますので、参拝の際、フンを踏まないように気を付けないといけませんが、そんなところも日常の中に禅を見出すスタイルの黄檗らしい光景でしょうか。
中国経済の好調に伴い、中国各地の寺院が復興され、ここ黄檗寺も永らくくたびれた大雄宝殿のみだったのが、2014年に訪れた時は復興の槌音高らかに大伽藍を建築中でしたが、景気の悪化か、2017年には工事の人影はなく、建築途中で放棄されたようなさびれた状態となっていました。村の人に状況を聞くと、なんでも数年前からお金が無くなり、工事もストップしたとのこと。
私が日本から来たと言ったら、日本のお金で完成させてほしいと懇願されてしまいました。
今でもおそらく工事はそのままで放置したままでしょう。寂しいことです。