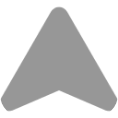特別編:国宝 円覚寺舎利殿

皆様、建築の森にようこそ。わたくし、「禅寺建築探検隊」案内係の佐々木でございます。
今回の探検は、本連載のタイトルに相応しく、皆様を円覚寺舎利殿(国宝)の内部へとお連れします。
このたび、円覚寺の横田南嶺管長様のご厚意により、舎利殿の中に足を踏み入れることをお許し頂き、細かい箇所まで写真に収めることができました。そして、それらの写真を「禅寺建築探検隊」に掲載することをご快諾頂けたのです。
そこで(まだ「第6の探検」の途中ではありますが)、今回は特別編として、皆様を円覚寺舎利殿の隅々までご案内することにいたします。
古建築に心惹かれる者にとって、円覚寺舎利殿はまさに「聖地」のような存在であります。
私は寺院建築の様式の一つである「禅宗様《ぜんしゅうよう》」の特徴を、この舎利殿の図面や写真を通して学びました。平面図も断面図も立面図も見てきましたが、いくら寸法が記されていても、図面だけを通して浮かび上がる全体象は、焦点の定まらない輪郭のぼやけたものでした。
いつか実際の建物に触れてみたい。そして建物に流れる時間を感じてみたい。折に触れそのように思っていたところ、今回ようやく長年の願いが叶うこととなりました。横田管長様には心より感謝申し上げます。
それでは、円覚寺舎利殿へと歩を進めてみたいと思います。
今回のテーマ:舎利殿から「禅宗様」を知る
舎利殿は室町中期の禅宗仏殿の典型として、古い時期の姿をとてもよく残している美しいお堂です。身舎《もや》の周囲に裳階《もこし》を廻らし、屋根が二重に重なって見えますが、杮葺き《こけらぶき》のため重苦しさがありません。
身舎の軒の反りは軽やかで美しく、裳階のなだらかな反りによって、反りの美しさがなお一層引き立ちます。さらに、着色の一切ない素木《しらき》の建物は、谷戸の新緑に生え清浄な美しさを醸し出しています。(画像1)

舎利殿の建立時期
現舎利殿が建立された正確な年はわかっていません。以前は弘安8年(1285)に造立され創建当時のまま現在に至る、とされていましたが、その後の調査研究の結果、建立後2度の焼失と再建を繰り返し、3度目の大火で焼失した際、太平寺客殿(仏殿)を移築したものが現舎利殿であることが明らかとなりました。
ただし、その太平寺客殿の建立時期には不明な点が多く、確実な時期はわかっていません。
ところが、舎利殿と瓜二つの仏殿、正福寺地蔵堂が東村山市にあり、その建立年代が確定しているため、それをもとに、舎利殿建立のおおよその時期を推定することができます。
正福寺地蔵堂は、昭和期の修理の際に発見された墨書によって、応永14年(1407)の建立であることが明らかとなりました。舎利殿はこの正福寺地蔵堂と、外観、内部の構成、装飾に至るまで酷似しているのです。そのため、舎利殿も同時期に建立されたものと考えられ、建立時期は15世紀前半頃、室町中期と想定されました。
「禅宗様」とは
今回、舎利殿の建築様式である「禅宗様」をご紹介いたしますが、その前に寺院建築における禅宗様の位置づけを説明いたしましょう。
寺院建築の様式は、大きく3種類に分けられます。平安時代に確立した「和様《わよう》」、鎌倉初期に重源が南宋の技法を取り入れ確立した「大仏様《だいぶつよう》」、栄西が魁《さきがけ》となり導入した南宋禅宗寺院の様式を、建長寺建立の際にさらに発展させ、様式として確立した「禅宗様」の3様式です。
建長寺は建長5年(1253)に南宋から渡来した禅僧、蘭渓道隆によって建立されました。中国の径山万寿寺の伽藍を模したとされ、創建当時の建物は残っていませんが、元弘元年(1331)の「建長寺指図写」からは、当時の伽藍配置が南宋の五山様式を踏襲していることが読み取れます。
南北朝期に五山十刹の制が定着すると、建長寺の構法は禅宗寺院建築の規範となり、やがて全国の禅宗寺院に影響を及ぼし、新しい構法は拡がっていきました。こうして、伽藍配置や平面、構造、意匠(デザイン)など、それぞれにおいて画期的で合理的な特徴を持つ「禅宗様」が確立されたのです。特に五山の仏殿は大規模なもので「円覚寺仏殿古図」元亀4年(1573)から正確な形式、規模を知ることができます。
「円覚寺仏殿古図」は、円覚寺大工高階家に伝わる中世の設計図(鎌倉国宝館に寄贈)で、「地割《じわり》之図」と「差図《さしず》」が描かれています。
「地割之図」は縮尺10分の1で描かれた、断面図と立面図を合わせた立断面図ですが、大工(棟梁)が直接線を引いていることから、建築設計も施工も大工が行う、という図式がわかります。
現在の円覚寺仏殿は鉄筋コンクリート造りではありますが、この図面をもとに、昭和39年に規模を小さくして外観を復元しています。
中世五山の大規模な仏殿は失われてしまいましたが、基本的な禅宗様としての構造が同じ建物は、今でも残っています。最古の仏殿は、鎌倉時代に建立された功山寺仏殿(1320)であり、そして室町中期建立の仏殿が円覚寺舎利殿なのです。
舎利殿で明らかなように、室町時代には「禅宗様」は定型化し、その後近世に至るまで、基本において崩れることなく用いられ、和様建築に大きな影響をもたらしたのでした。
円覚寺舎利殿における禅宗様
それでは円覚寺舎利殿のどの部分が禅宗様の特徴を示しているのか、見てみたいと思います。
正面

まず正面に立ってみます(画像2)。ここ(裳階《もこし》)は、禅宗様のデザイン性が最も強く感じられる部分です。
中央間に「棧唐戸《さんからど》」、両脇間の戸口に「花頭枠《かとうわく》(画像3)」、両端に「花頭窓」(画像4)が独特の曲線(花頭曲線)に縁どられ整然と並んでいます。
棧唐戸は薄い板をパッチワークのように框などで押さえてあるため軽く、戸口の上下につけられた「藁座《わらざ》(画像5)」に差し込まれた軸で開閉します。
欄間は「弓欄間《ゆみらんま》(画像6)」で、弓の形をした連子が連なり、中央には宝珠が飾られます。建物内部から眺めると、弓型の連子から差し込む光が仄暗い堂内を穏やかな明かりで満たしています。




柱
次は柱を見てみましょう(画像7)。柱は円柱で、上部と下部には、丸みをもってすぼまった粽《ちまき》が付いています。方形の「礎石《そせき》」の上に置かれた「礎盤《そばん》」上に柱は立ち、何本もの貫《ぬき》でつながれます。貫は細い部材ながら堅固に建物を固めています(画像8)。平安時代までには現れなかった部材の一つです。



粽付き柱の上に台輪
組物
(画像9)は裳階部分の組物ですが、ここにも禅宗様の大きな特徴がみられます。柱の上に直接組物が載るのではなく、柱の上には盤状の台輪《だいわ》が載り、その上に組物が収まっています。組物の部材の一つ、肘木《ひじき》にも注目してください。
台輪の上には組物を構成する四角い斗《ます》が載り、その上に舟形をした肘木が組まれ、組物を形成しています。その肘木の下部の曲線は、四分の一の円弧を描いています。禅宗様の肘木の形です。
台輪は建物の隅まで延び、そこで交差します(画像10)。

交差部分は台輪を載せる頭貫《かしらぬき》とともに柱からはみ出し、木鼻《きばな》を形成しています。木鼻には繰形《くりがた》が施され、渦巻紋様(絵様)が彫刻されていますが、この場所以外にも部材の端部(木鼻)に繰形や絵様が施され、華やかさを演出しており、これも禅宗様の特徴の一つといえます。
右側の木鼻は昭和42年の修理の際、取り替えられたもので、左側は旧材だと思われます。旧材の木鼻は繰形の形が崩れ、紋様も消えています。彫りの浅い室町期の特徴がとてもよく理解できます。近世になると紋様は深く鋭く彫られるように変化しますので、時代を判断する部材と言えます。
屋根
次に建物の横側に移動し、屋根の妻側を見てみましょう(画像11)。三角の部分、妻飾り《つまかざり》には、三角形の位置に並んでいる部材、懸魚《げぎょ》が掛けられています。これらは内部の部材が直接雨風に当たらぬように取り付けられたものです。
これらのデザインは三ッ花懸魚《みつばなげぎょ》とよばれ、中国伝来のものです。その奥に見える横材は虹梁《こうりょう》で、そこに大瓶束《たいへいづか》が載っていますが、ここにも禅宗様の部材が使われています。

目を転じて屋根の下を見てみましょう。建物の軒部分は圧巻です(画像12)。組物は隙間なく詰め込まれており、この並べ方を「詰組《つめぐみ》」と呼び、禅宗様の大きな特徴の一つになっています。

軒を支える垂木が放射状に並んでいることにお気づきでしょうか。狂いなく少しずつ垂木の間隔を広げた様は扇の骨組みのように繊細です。この垂木の並べ方を、扇垂木《おうぎだるき》と呼び、組物と共に、華やかさを醸し出しています。
また組物の中から突き出している尾垂木《おだるき》は細く、上に反っています(画像13)。奈良時代の建物、薬師寺東塔や唐招提寺金堂に用いられている尾垂木と比較すると、極めて華奢であることが実感できます。

堂内
それではお堂の中に足を踏み入れましょう。内部は土間床です。木の床は張られていません。和様の仏堂は日本の生活様式に合わせ、床が張られ周りに縁がめぐらされていますが、禅宗様は中国の仏堂の影響を受け確立した様式ですから土間床なのです。

この写真は裳階部分です。(画像14)海老のような形のものが浮かんでいるように見えますが、これは海老虹梁《えびこうりょう》と呼ばれています。海老虹梁は、左側の身舎空間を構成する柱(身舎柱・入側柱)と右側裳階空間を構成する柱(裳階柱・側柱)とをつなぐ重要な役割を果たす部材です。
身舎
いよいよ身舎に入ります。身舎は建物の中心となる空間です。舎利殿には仏牙舎利が祀られている聖域ですから、その空間に相応しい荘厳な趣を醸しだしています。何より、その高さと広さに驚かされます。裳階から身舎に歩を進めた瞬間、押さえられていたものが一気に解放されたような衝撃を受けます(画像15)。


身舎の平面自体はそれほど広くはないのですが、厨子の後ろにある来迎柱(黒漆塗り)以外、内側に柱がないせいか意外なほど広さが感じられます。設計者もこのような意図を持っていたのでしょう。柱が無くても身舎空間を支えられるように上方に工夫がされているのです。(画像16)
頭上には身舎柱と来迎柱とをつなぐ大きな部材、大虹梁《だいこうりょう》が2丁横たわっています(画像15、16)。身舎は、柱や貫、板壁、頭貫、台輪を組んで固めた箱のような形をしており、本来は内部にも柱を立たせないと、さらに上方に組み立てる小屋組みが崩れてしまいます。けれどもこの大虹梁が来迎柱と身舎柱を橋のように渡し繋ぎ、さらにその上に大瓶束《たいへいづか》(画像17)を載せることで柱を減らす(減柱)ことを可能にしたのです。


大瓶束は鏡天井《かがみてんじょう》をより高く持ち上げるための役割も担っています。大瓶束が天井の枠となる部材を支え、その枠の周囲には天井の高さを増すために組物が組まれ、それが中央に向かってせり上がり板張りの鏡天井を支えています。こうして天井はより一層、高さを増しているのです(画像16)
身舎を広く高く感じさせる仕掛けはまだあります。軒で放射状に並んだ扇垂木は、建物内側奥深く、鏡天井の上まで引き込まれていきます。急な勾配で整然と立ち並ぶ垂木は堂内全体を囲い、空間に上昇のリズムを作り上げています(画像18)。

垂木の規則正しい連なりにアクセントをつけ、上昇のリズムをさらに強調しているのは尾垂木とそれを支える持送り《もちおくり》です(画像19)。
身舎の軒の組物から突き出ているように見えた尾垂木(画像13)は、実は建物内部の奥から伸びていることが確認できます。建物の内側で尾垂木の根元部分が上からの荷重を受け、さらに持送りが斜め下から支えています。そして建物の外側で梃子の働きによって軒を支えることで、あの美しい軒の反りが作られていたのです。(画像19)
舎利殿の見事な木組みは、上からかかる力を下へ下へと流す的確な構造を示しています。仏様を祀るために、部材の一つ一つが正確に丁寧に美しく仕上げられている、それこそが、身舎に漂う荘厳な趣を生み出しているのでしょう。写真を拡大してみますと、改めてきれいな仕上げに心を打たれます。
近世になると、禅宗様の仏堂には天井が全面に張られるようになります。迫力ある雲竜図などは天井の広さが生み出したものですが、舎利殿に感じられるこの厳かさは中世建築だけが持つものです。この意味でも、円覚寺舎利殿は非常に貴重なお堂である、と再認識した次第です。
今回の貴重な機会を頂けましたこと、円覚寺様に心より感謝申し上げます。
取材協力:臨済宗円覚寺派 大本山 円覚寺
https://www.engakuji.or.jp
前回の続編「第6の探検 – 扉、その仕組みと変遷(3)」は、8月掲載予定です。おたのしみに!